 |
[ HOME>日本の今を考える>『この国のかたち』を考える ] |
 |
[ HOME>日本の今を考える>『この国のかたち』を考える ] |
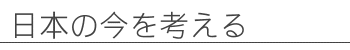 |
||
『この国のかたち』を考える |
||
過去の歴史を書き換えることはできても、過去の事実そのものを変えることはできない。しかし、人は今に生き、未来を創造できる。 このコーナーでは、憲法や行政法の基礎知識を前提に、将来の日本を担うであろう人たちと一緒に「この国のかたち」を考えてみたい。 |
||
|
||
| はじめに 過去の歴史を書き換えることはできても、過去の事実そのものを変えることはできない。しかし、人は今に生き、未来を創造できる。 今回は、「政・官・業のトライアングル」というテーマで、政治家・官僚・業界の関係について分析する。 国会議員の憲法上の地位 憲法上、国会議員は「全国民の代表」である(43条1項)。日本を代表する有力な学説によると「全国民の代表」には、「政治的代表」という意味に加え、「社会学的代表」いう意味も含まれる(芦部信喜『憲法』<岩波書店>第三版p266参照)。 ここで、「政治的代表」(「純粋代表」ということもある)とは、代表機関の行為が法的に代表される国民の行為とみなされるという趣旨の法的な意味ではなく、国民は代表機関を通じて行動し、代表機関は国民意思を反映するものとみなされるという趣旨の政治的な意味である。 また、「社会学的代表」(半代表ということもある)とは、国民意思と代表者意思の事実上の類似が重視されなければならないという考え方である。 簡単に言うと、国会議員は、「全国民の代表」であるから、国民の意思に縛られることなく、自己の信念に基づいてのみ発言・表決できる(これを「自由委任」と言う)が、他方で多様な国民意思をできるかぎり国会に反映させなければならないということである。 国会議員の本音 しかし、憲法の建前は建前として、国会議員になること自体、金・時間など膨大なコストがかかり実に大変である。しかも、国会議員も「選挙に落ちればただの人」(失業者)である。何としても当選しなければならない。当選するためには、有権者の支持を受けなければならない。有権者の支持を受けるためには、有権者の利益や便宜を図らなければならない。有権者といっても、選挙に来てくれるかどうかわからないような有権者(政治的無関心層や浮動票)は全く当てにならない。当てになるのは、真剣に選挙を応援し、確実に自分に一票を投じてくれる人である。したがって、どうしても業界関係者や地元の優力者の力を頼りにしなければならなくなる。 もともと議員になろうという人は「人から頼まれたら嫌とは言えない性格の人」が多い。熱心な有権者の意見に耳を傾けるのは人の感情として当然とも言える。そこで、「熱心な有権者の意見に一生懸命に耳を傾けて何が悪い(社会学的代表)。私も全国民の代表者なのだ(政治的代表)」と開き直られたら、憲法の理念もそれで一巻の終わりなのである。 官僚の憲法上の地位 キャリア官僚に目を転ずる。 キャリア官僚といえども国家議員と同じく「全体の奉仕者」(国民に対するサービス機関)である。しかし、キャリア官僚は国民によって選ばれていない。そこで、国民主権(前文・1条)や国民の公務員の選定・罷免権(15条1項)と矛盾するのではないかという疑問が生ずる。 しかし、キャリア官僚の任命権は各省大臣(過半数は国会議員)にある。日本のキャリア・システムは任免権(任命権と罷免権)が各省大臣にあること、法律によって行動活動が縛られていること(法律による行政の原理)、国家行政組織の基本的部分が法律事項とされていることによって国民主権原理となんとか調和するのである。 官僚の本音 しかし、キャリア官僚の多く、特に上級のキャリアは主権者である国民の側を向いていない。キャリア官僚は専門家であり、国民は素人であり指導・教育しなければならない存在である。個々の国民は全く怖くない。 しかし、素人だが怖いのは何と言っても任命権と罷免権のある大臣であり、大臣経験のある(あるいはなりそうな)族議員である。彼らに逆らったら政策の実現は不可能だし、出世もない。課長で終わるか、局長で終わるか、事務次官まで登りつめるかで、退職金だけでも数千万円単位で異なってくる。出世を望むなら、どうでしても政治家の言いなりにならざるを得ない。その政治家は業界や地元の言いなりである。 結局、理想はあっても、現実には官僚は政治家を通じ業界や地元の意向を受けて、企画・立案をし、法律や予算を組まざるを得ない。 政・官・業のトライアングル その結果、業界関係者や地元有力者は、自分達の利益のために政治家を通じて官僚を使い法律や予算を組ませ、政治家はその尽力の見返りとして票を貰う。官僚は政治家に言いなりになることによって出世が約束される。こうして政・官・業の(「魔の」とか「鉄の」といった修飾語がつくこともある)トライアングルができあがる。 別の見方をすれば、「国民(ただし業界関係者・地元有力者だけ)は政治家に強く、官僚に弱い。政治家(ただし与党の有力議員だけ)は官僚に強く、国民に弱い。官僚は国民に強いが、政治家に弱い」という三すくみの関係が成立している。 注意しなければならないのは、蚊帳の外に置かれているのは業界関係者や地元関係者以外の一般国民である。この人たちは政治家からも官僚からも全く相手にされていない。 選挙に行かない国民の責任 実は、「政・官・業のトライアングル」を放任しているのは、選挙に行かない国民なのである。 マスメディアから「浮動票の動向が今後の政局を決める」とおだてられ、「ろくな政治家がいないから投票には行かない」と格好をつけてみても、一番損をしているのは自分達なのである。例えば、国債・公債や年金の問題についても一番損をするのは20代・30代なのに投票率は一番低い。これでは20代・30代に配慮した法律や予算が組まれるはずもない。 選挙に行かないことによって投票率は下がり、相対的に業界の組織票に頼る国会議員が有利となる。小選挙区で投票率が仮に50%とすると、その過半数、すなわち有権者のわずか25%(4人に1人)超の支持を受けている国会議員が楽々と当選することになる。業界の支持を受けた国会議員は、当選することにより業界の有り難味が骨身に沁みて、ますます業界や地元に忠誠を尽くす。 不良債権処理が進まない理由 今、日本経済を蝕んでいる不良債権処理が進まないのも、それによって大量の失業者が発生する危険性があるからでもあるが、不良債権処理をすることによって、公的資金を注入され経営責任を追及される可能性のある銀行、倒産の危険性のある建設、不動産、流通業界が今まで、熱心に与党に政治献金をし、選挙を応援してきた日ごろ努力の成果とも言える。 不良債権処理の目的は、自由で公正な経済秩序を確保することにある(木村剛『日本 ニッポン・スタンダード 資本主義の哲学』<PHP出版>参照)。非効率な産業が市場から退散しないで残っているということは、限られた資金・資源・人材が有効に活用されていないということを意味する。 したがって、不良債権処理をしないことは、短期的には雇用は確保されるとしても、長期的に見た場合、望ましいわけではない。 国民の大多数の人に必要なのは、不良債権処理を進めるに当たってのセーフティ・ネットの構築と新産業の保護・育成のための政策なのである。 しかし、今のところ具体的かつ有効な政策はどの政党からも明確な形で提示・実行されてはいないように思われている。 政界再編成の必要性 熱心な有権者の意向を受けて、国会議員が動き、その指示を受けて官僚が動くというのも自然といえば自然なのである。業界や地元のことしか考えない国会議員がいてもやむを得ない。「国家全体のことをもっと考えろ!」と言ってもある意味では無駄である。 しかし、現実には、業界や地元(有力者)の利益とは直接には関係のない国民がはるかに多い。この人達に本当に必要な政策が必要である。そのためには若手(年齢的な意味ではなく、柔軟性のある思考の出来る人)を中心とした政界の再編成が必要なのかもしれない。 若きサムライ 官僚も大臣の任免権と指揮監督権に服する以上、与党の言いなりになるのは当然といえば当然である。 しかし、官僚には選挙がない分、専門家として長期的視点に立った企画・立案ができる立場にある。幾つかの選択肢を国民や政治家に提示することによって、再び国民の信頼を取り戻すことが可能ではないか。 上司や大臣に進言して受け入れられなければ、辞めて政界に転出するようなサムライの覚悟(魂)も必要である。 主権者としての教育の重要性 国民も目先の利益のことだけ考えるのではなく、もう少し先の自分の生活や子孫のことまで考えなければならない。 しかし、国民は政治や経済に関する知識が今までの教育では充分与えられていない。自分で「考える力」もあまりない。もちろん、特定の思想を教えることは憲法19条違反である(憲法19条「思想及び良心の自由は、これを保障する」)。 大事なのは政治や経済に関する基本的枠組みや基礎的知識(歴史など)の教育である。本稿もその試みの1つである。 今回の結論(自立した国民) ただ、最近では、国民も構造不況の中で、声を上げ始めた。政治家のありかた、官僚のありかた、政策や法案の内容、予算の組み方や使い方にマスメディアや国民も厳しい目を向け始めた。 情報公開法1条の目的規定から「監視」と「参加」の語句は削除されてしまったが、これからは、国民自身が自立し、よりましな政治家を選び、行政活動に対してもより積極的に「監視」し、「参加」していかなければならない。 |
||
| ※本稿は、『Civil Service』(早稲田経営出版)2003年2、3月号に掲載された原稿を一部抜粋し、加筆したものです。 | ||
| ©1999-2003 The Future |