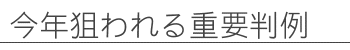【判旨】
「一 原審が適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
1 平成元年7月8日午前4時30分ころ、Aは、突然の背部痛で目を覚まし、庭に出たところ、しばらくして軽快した。
その後、妻である被上告人Y1の強い勧めもあって、Aは、子の被上告人Y2と共に自動車で上告人の経営するB総合病院に向かった。
自宅から上告人病院までは車で6、7分くらいの距離であり、当初A自身が運転していたが、途中で背部痛が再発し、被上告人Y2が運転を替わった。
2 午前5時35分ころ、Aは上告人病院の夜間救急外来の受付を済ませ、その後間もなくして、外来診察室において、C医師の診察が開始された。
3 Aの主訴は、上背部(中央部分)痛及び心か部痛であった。
触診所見では心か部に圧痛が認められたものの、聴診所見では、特に心雑音、不整脈等の異常は認められなかった。
Aは、C医師に対し、7、8年前にも同様の痛みがあり、そのときは尿管結石であった旨伝えた。
C医師は、Aの痛みから考えて、尿管結石については否定的であったが、念のため尿検査を実施した。
その結果、潜血の存在が否定されたので、その時点でC医師は、症状の発現、その部位及び経過等から第一次的に急性すい炎、第二次的に狭心症を疑った。
4 次にC医師は、看護婦に鎮痛剤を筋肉内注射させ、さらに、Aを外来診察室の向かいの部屋に移動させた上で、看護婦に急性すい炎に対する薬を加えた点滴を静注させた。
なお、診察開始からAが点滴のために診察室を出るまでの時間は10分くらいであった。
5 点滴のための部屋に移ってから5分くらい後、Aは、点滴中突然「痛い、痛い」と言い、顔をしかめながら身体をよじらせ、ビクッと大きくけいれんした後、すぐにいびきをかき、深い眠りについているような状態となった。
被上告人Y2の知らせで向かいの外来診察室からC医師が駆けつけ、呼びかけをした。
しかし、ほどなく、呼吸が停止し、C医師がAの手首の脈をとったところ、触知可能ではあったが、極めて微弱であった。
そこで、C医師は体外心マッサージ等を始めるとともに、午前6時ころ、Aを2階の集中治療室に搬入し、駆けつけた他の医師も加わって各種のそ生術を試みたが、午前7時45分ころ、Aの死亡が確認された。
6 Aは、自宅において狭心症発作に見舞われ、病院への往路で自動車運転中に再度の発作に見舞われ、心筋こうそくに移行していったものであって、診察当時、心筋こうそくは相当に増悪した状態にあり、点滴中に致死的不整脈を生じ、容体の急変を迎えるに至ったもので、その死因は、不安定型狭心症から切迫性急性心筋こうそくに至り、心不全を来したことにある。
7 背部痛、心か部痛の自覚症状のある患者に対する医療行為について、本件診療当時の医療水準に照らすと、医師としては、まず、緊急を要する胸部疾患を鑑別するために、問診によって既往症等を聞き出すとともに、血圧、脈拍、体温等の測定を行い、その結果や聴診、触診等によって狭心症、心筋こうそく等が疑われた場合には、ニトログリセリンの舌下投与を行いつつ、心電図検査を行って疾患の鑑別及び不整脈の監視を行い、心電図等から心筋こうそくの確定診断がついた場合には、静脈留置針による血管確保、酸素吸入その他の治療行為を開始し、また、致死的不整脈又はその前兆が現れた場合には、リドカイン等の抗不整脈剤を投与すべきであった。
しかるに、C医師は、Aを診察するに当たり、触診及び聴診を行っただけで、胸部疾患の既往症を聞き出したり、血圧、脈拍、体温等の測定や心電図検査を行うこともせず、狭心症の疑いを持ちながらニトログリセリンの舌下投与もしていないなど、胸部疾患の可能性のある患者に対する初期治療として行うべき基本的義務を果たしていなかった。
8 C医師がAに対して適切な医療を行った場合には、Aを救命し得たであろう高度の蓋然性までは認めることはできないが、これを救命できた可能性はあった。
二 原審(東京高裁、「重判」の方が詳しいので参照:筆者注)は、右事実関係に基づき、C医師が、医療水準にかなった医療を行うべき義務を怠ったことにより、Aが、適切な医療を受ける機会を不当に奪われ、精神的苦痛を被ったものであり、同医師の使用者たる上告人は、民法715条に基づき、右苦痛に対する慰謝料として200万円を支払うべきものとした。
論旨は、原審の右判断を不服とするものである。
(以下、最高裁の見解:筆者注)
三 本件のように、疾病のため死亡した患者の診療に当たった医師の医療行為が、その過失により、当時の医療水準にかなったものでなかった場合において、右医療行為と患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されないけれども、医療水準にかなった医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明されるときは、医師は、患者に対し、不法行為による損害を賠償する責任を負うものと解するのが相当である。
けだし、生命を維持することは人にとって最も基本的な利益であって、右の可能性は法によって保護されるべき利益であり、医師が過失により医療水準にかなった医療を行わないことによって患者の法益が侵害されたものということができるからである。
原審は、以上と同旨の法解釈に基づいて(←本件東京高裁と最高裁は全く異なる立場という学者の指摘がある:筆者注)、C医師の不法行為の成立を認めた上、その不法行為によってAが受けた精神的苦痛に対し同医師の使用者たる上告人に慰謝料支払の義務があるとしたものであって、この原審の判断は正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。」
【判例のポイント】
1.本件において、医師が患者に対して適切な医療を行った場合には、患者を救命し得たであろう「高度の蓋然性」までは認めることはできないが、これを「救命できた可能性」はあった。
2.疾病のため死亡した患者の診療に当たった医師の医療行為が、その過失により、当時の医療水準にかなったものでなかった場合において、「右医療行為と患者の死亡との間の因果関係の存在」は証明されないけれども、「医療水準にかなった医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在」が証明されるときは、医師は、患者に対し、不法行為による損害を賠償する責任を負う。
3.「生命を維持すること」は人にとって最も基本的な利益であって、右の「可能性」は法によって保護されるべき利益であり、医師が過失により医療水準にかなった医療を行わないことによって患者の法益が侵害されたものということができる。
4.本件において、医師の不法行為が成立し、その不法行為によって患者が受けた「精神的苦痛」に対し同医師の使用者たる病院に「慰謝料」支払の義務がある。
【ワンポイントレッスン】
1.まず、本件では、患者を救命し得たであろう「高度の蓋然性」までは認められず、「医療行為」と患者の「死亡」(被侵害利益は生命)との間の「因果関係」の存在は証明されていない。
仮に「高度の蓋然性」があれば、平成11.2.25(百選II・78=判例六法・民法709条47番)の射程距離内でカバーできた。
そこで、本判決は、「相当程度の生存可能性」自体が不法行為の「被侵害利益」となることを認め、その「効果」として「慰謝料請求権」を認めるというルールを示した。
最高裁は具体的数字を示していないが、鑑定人の鑑定では、本件患者の「救命可能性20%以下」とされており、かなり緩やかに不法行為の成立を認める基準であると思われる。
択一試験対策としては、以上の単純な理解で十分である。
2.以下は、上級者向けに、原審(東京高裁)と最高裁との違いについて解説する。
|
被侵害利益 |
救命可能性 |
損害賠償 |
| 東京高裁 |
適切な医療を受ける期待 |
不要 |
慰謝料 |
| 最高裁 |
相当程度の生存可能性 |
必要 |
慰謝料 |
上図のように、両者は全く異なる立場に立ち、最高裁の「原審は、以上と同旨の法解釈に基づいて…」という部分は、「重判」を事実の概要の最初から読んだ人は、「オイオイ、全然違うだろ?」と独り言でツッコミを入れたはずである(国
I 受験生でなんとも思わなかった人は反省しよう)。
また、最高裁が、損害賠償を「慰謝料」という「非・財産的損害」に限定している点もおかしい。
「生存可能性」を前提とするなら、それに対応した収入の喪失など「財産的損害」も含むのが、理論的に整合する。
というわけで、かなりアヤシイ判例であるが、とりあえず判旨を丸暗記しておこう。
【試験対策上の注意点】
択一試験で今後出題される可能性が高い。
平成11.2.25(百選II・78=判例六法・民法709条47番)とセットで押さえておこう。