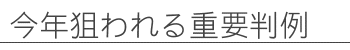【判旨】*筆者注:事実関係は読み飛ばしても構わない
「一 本件において、大嶋一郎の相続人である平成一〇年(オ)第二一七号被上告人ら・同第二一八号上告人ら(以下、それぞれを「一審原告久光」のようにいい、右両名を併せて「一審原告ら」という。)は、平成一〇年(オ)第二一七号上告人・同第二一八号被上告人(以下「一審被告」という。)に対し、一郎の一審被告に対する民法七一五条に基づく損害賠償請求権を相続したとして、その支払を求めているところ、所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、首肯するに足りる。
これによると、本件の事実関係の概要は、次のとおりである。
1 大嶋一郎は、昭和四一年一一月三〇日、一審原告らの長男として出生した。
一郎は、健康で、スポーツが得意であり、その性格は、明朗快活、素直で、責任感があり、また、物事に取り組むに当たっては、粘り強く、いわゆる完ぺき主義の傾向もあった。
平成二年から三年当時、一郎と一審原告らは同居しており、一審原告らはそれぞれ職を有していた。
2 一郎は、平成二年三月に明治学院大学法学部を卒業し、同年四月一日、一審被告の従業員として採用され、他の一七八名と共に入社した。
採用の約二か月前に一郎に対して行われた健康診断においては、色覚異常があるとされたほかは、格別の問題の指摘はなかった。
3 新入社員研修を終え、一郎は、平成二年六月一七日、一審被告のラジオ局ラジオ推進部に配属された。
同部の部長は滝口昌明で、同部には一三名の従業員が所属し、二つの班に分けられていた。
一郎は、坂本康治を班長とする班に属するものとされて、坂本外二名の従業員と共に、築地第七営業局及び入船第八営業局関係の業務を担当することとなった。
4 平成二年当時、一審被告の就業規則においては、休日は原則として毎週二回、労働時間は午前九時三〇分から午後五時三〇分までの間、休憩時間は正午から午後一時までの間とされていた。
そして、平成一〇年法律第一一二号による改正前の労働基準法三六条の規定に基づき一審被告と労働組合との間で締結された協定(以下「三六協定」という。)によって、各労働日における男子従業員のいわゆる残業時間の上限は、六時間三〇分とされ、平成二年七月から平成三年八月までの間の各月の合計残業時間の上限は、ラジオ推進部の場合、別紙の「月間上限時間」欄記載のとおりとされていた。
ところで、一審被告においては、残業時間は各従業員が勤務状況報告表と題する文書によって申告することとされており、残業を行う場合には従業員は原則としてあらかじめ所属長の許可を得るべきものとされていたが、実際には、従業員は事後に所属長の承認を得るという状況となっていた。
一審被告においては、従業員が長時間にわたり残業を行うことが恒常的に見られ、三六協定上の各労働日の残業時間又は各月の合計残業時間の上限を超える残業時間を申告する者も相当数存在して、労働組合との間の協議の席等において問題とされていた。
さらに、残業時間につき従業員が現に行ったところよりも少なく申告することも常態化していた。
一審被告は、このような状況を認識し、また、残業の特定の職場、特定の個人への偏りが問題であることも意識していた。
一審被告は、午後一〇時から午前五時までの間に業務に従事した従業員について所定労働時間に対する例外的取扱いを認める制度を設けていたほか、午前零時以降に業務が終了した従業員で翌朝定時に出勤する者のために一審被告の費用で宿泊できるホテルの部屋を各労働日において五室確保していたが、一審被告による周知徹底の不足等のため、これらは、新入社員等には余り利用されていなかった。
5 一郎は、ラジオ推進部に配属された当初は、班長付きと称される立場にあって、日中はおおむね坂本と共に行動していた。
その業務の主な内容は、企業に対してラジオ番組の提供主となるように企画書等を用いて勧誘することと、企業が宣伝のために主宰する行事等の企画立案及び実施をすることであった。
一郎は、労働日において、午前八時ころまでに自宅を出て、午前九時ころまでに出勤し、執務室の整理など慣行上新入社員が行うべきものとされていた作業を行った後、日中は、ほとんど、勧誘先の企業や一審被告の他の部署、製作プロダクション等との連絡、打合せ等に忙殺され、午後七時ころに夕食を取った後に、企画書の起案や資料作り等を開始するという状況であった。
一郎は、業務に意欲的で、積極的に仕事をし、上司や業務上の関係者から好意的に受け入れられていた。
6 平成二年七月から平成三年八月までの間に一郎が勤務状況報告表によって申告した残業時間の各月の合計は、別紙の「申告残業時間」欄に記載のとおりである。
しかしながら、右申告に係る残業時間は、実際の残業時間よりも相当少なく、また、右各月において一郎が午前二時よりも後に退勤した回数は、別紙の「午前二時以降退勤」欄に記載のとおりであった(同欄の括弧内の数字は、右のうち終夜退勤しなかった回数である。)。
一郎は、退勤するまでの間に、食事、仮眠、私事等を行うこともあったが、大半の時間をその業務の遂行に充てていた。
7 一郎は、ラジオ推進部に配属されてからしばらくの間は、出勤した当日中に帰宅していたが、平成二年八月ころから、翌日の午前一、二時ころに帰宅することが多くなった。
同月二〇日付けの滝口の一郎に対する助言を記載した文書には、一郎の業務に対する姿勢や粘り強い性格を評価する記載と共に、今後は一定の時間内に仕事を仕上げることが重要である旨の記載があった。
一方、一郎は、同年秋ころに一審被告に提出した文書において、自分の企画案が成功したときの喜びや、思っていた以上に仕事を任せてもらえるとの感想と共に、業務に関する不満の一つとして、慢性的に残業が深夜まであることを挙げていた。
なお、同年秋に実施された一郎に対する健康診断の結果は、採用前に実施されたものの結果と同様であった。
8 一郎は、平成二年一一月末ころまでは、遅くとも出勤した翌日の午前四、五時ころには帰宅していたが、このころ以降、帰宅しない日や、一審原告久光が利用していた東京都港区内所在の事務所に泊まる日があるようになった。
一審原告らは、一郎が過労のために健康を害するのではないかと心配するようになり、一審原告久光は、一郎に対し、有給休暇を取ることを勧めたが、一郎は、自分が休んでしまうと代わりの者がいない、かえって後で自分が苦しむことになる、休暇を取りたい旨を上司に言ったことがあるが、上司からは仕事は大丈夫なのかと言われており、取りにくいと答えて、これに応じなかった。
9 平成三年一月ころから、一郎は、業務の七割程度を単独で遂行するようになった。
このころに一郎が一審被告に提出した文書には、業務の内容を大体把握することができて計画的な作業ができるようになった旨の記載のほか、今後の努力目標として効率的な作業や時間厳守等を挙げる記載や、担当業務の満足度に関して仕事の量はやや多いとする記載等があった。
一郎の業務遂行に対する上司の評価は概して良好であり、滝口らがこのころに作成した文書には、非常な努力家であり先輩の注意もよく聞く素直な性格であるなどと評価する記載があった。
10 滝口は、平成三年三月ころ、坂本に対し、一郎が社内で徹夜していることを指摘し、坂本は、一郎に対し、帰宅してきちんと睡眠を取り、それで業務が終わらないのであれば翌朝早く出勤して行うようにと指導した。
このころの滝口らの一郎についての評価は、採用後の期間を考慮するとよく健闘しているなどというものであった。
平成二年度において一郎が取得することができるものとされていた有給休暇の日数は一〇日であったが、一郎が実際に取得したのは〇・五日であった。
11 一郎の所属するラジオ推進部には、平成三年七月に至るまで、新入社員の補充はなかった。
同月以降、一郎は、班から独立して業務を遂行することとなり、築地第七営業局関係の業務と入船第三営業局関係の業務の一部を担当し、入船第八営業局関係の業務の一部を補助するようになった。
このころ、一郎は、出勤したまま帰宅しない日が多くなり、帰宅しても、翌日の午前六時三〇分ないし七時ころで、午前八時ころまでに再び自宅を出るという状況となった。
一審原告洋子は、栄養価の高い朝食を用意するなどして一郎の健康に配慮したほか、自宅から最寄りの駅まで自家用車で一郎を送ってその負担の軽減を図るなどしていた。
これに対し、一審原告久光は、一郎と会う時間がほとんどない状態となった。
一審原告らは、このころから、一郎の健康を心配して体調を崩し、不眠がちになるなどしていた。
一方、一郎は、前述のような業務遂行とそれによる睡眠不足の結果、心身共に疲労困ぱいした状態になって、業務遂行中、元気がなく、暗い感じで、うつうつとし、顔色が悪く、目の焦点も定まっていないことがあるようになった。
このころ、坂本は、一郎の健康状態が悪いのではないかと気付いていた。
12 一郎は、平成三年八月一日から同月二三日までの間、同月三日から同月五日までの間に旅行に出かけたほかは、休日を含めてほぼ毎日出社した。
一郎は、右旅行のため同月五日に有給休暇を取得したが、これは、平成三年度において初めてのものであった。
一郎は、同月に入って、坂本に対し、自分に自信がない、自分で何を話しているのか分からない、眠れないなどと言ったこともあった。
13 平成三年八月二三日、一郎は、午後六時ころにいったん帰宅し、午後一〇時ころに自宅を自家用車で出発して、翌日から取引先企業が長野県内で行うこととしていた行事の実施に当たるため、同県内にある坂本の別荘に行った。
この際、坂本は、一郎の言動に異常があることに気付いた。
一郎は、翌二四日から同月二六日までの間、右行事の実施に当たり、その終了後の二六日午後五時ころ、行事の会場を自家用車で出発した。
14 一郎は、平成三年八月二七日午前六時ころに帰宅し、弟に病院に行くなどと話し、午前九時ころには職場に電話で体調が悪いので会社を休むと告げたが、午前一〇時ころ、自宅の風呂場において自殺(い死)していることが発見された。
15 うつ病は、抑うつ、制止等の症状から成る情動性精神障害であり、うつ状態は、主観面では気分の抑うつ、意欲低下等を、客観面ではうち沈んだ表情、自律神経症状等を特徴とする状態像である。うつ病にり患した者は、健康な者と比較して自殺を図ることが多く、うつ病が悪化し、又は軽快する際や、目標達成により急激に負担が軽減された状態の下で、自殺に及びやすいとされる。
長期の慢性的疲労、睡眠不足、いわゆるストレス等によって、抑うつ状態が生じ、反応性うつ病にり患することがあるのは、神経医学界において広く知られている。
もっとも、うつ病の発症には患者の有する内因と患者を取り巻く状況が相互に作用するということも、広く知られつつある。
仕事熱心、凝り性、強い義務感等の傾向を有し、いわゆる執着気質とされる者は、うつ病親和性があるとされる。
また、過度の心身の疲労状況の後に発症するうつ病の類型について、男性患者にあっては、病前性格として、まじめで、責任感が強すぎ、負けず嫌いであるが、感情を表さないで対人関係において敏感であることが多く、仕事の面においては内的にも外的にも能力を超えた目標を設定する傾向があるとされる。
前記のとおり、一郎は、平成三年七月ころには心身共に疲労困ぱいした状態になっていたが、それが誘因となって、遅くとも同年八月上旬ころに、うつ病にり患した。
そして、同月二七日、前記行事が終了し業務上の目標が一応達成されたことに伴って肩の荷が下りた心理状態になるとともに、再び従前と同様の長時間労働の日々が続くことをむなしく感じ、うつ病によるうつ状態が更に深まって、衝動的、突発的に自殺したと認められる。
(筆者注:試験対策上は以下から重要)
二 以上の事実に基づいて、一審被告の民法七一五条に基づく損害賠償責任を肯定した原審の判断について検討する。
1 労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。
労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法六五条の三は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される。
これらのことからすれば、使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである。
2 一審被告のラジオ局ラジオ推進部に配属された後に一郎が従事した業務の内容は、主に、関係者との連絡、打合せ等と、企画書や資料等の起案、作成とから成っていたが、所定労働時間内は連絡、打合せ等の業務で占められ、所定労働時間の経過後にしか起案等を開始することができず、そのために長時間にわたる残業を行うことが常況となっていた。
起案等の業務の遂行に関しては、時間の配分につき一郎にある程度の裁量の余地がなかったわけではないとみられるが、上司である滝口らが一郎に対して業務遂行につき期限を遵守すべきことを強調していたとうかがわれることなどに照らすと、一郎は、業務を所定の期限までに完了させるべきものとする一般的、包括的な業務上の指揮又は命令の下に当該業務の遂行に当たっていたため、右のように継続的に長時間にわたる残業を行わざるを得ない状態になっていたものと解される。
ところで、一審被告においては、かねて従業員が長時間にわたり残業を行う状況があることが問題とされており、また、従業員の申告に係る残業時間が必ずしも実情に沿うものではないことが認識されていたところ、滝口らは、遅くとも平成三年三月ころには、一郎のした残業時間の申告が実情より相当に少ないものであり、一郎が業務遂行のために徹夜まですることもある状態にあることを認識しており、坂本は、同年七月ころには、一郎の健康状態が悪化していることに気付いていたのである。
それにもかかわらず、滝口及び坂本は、同年三月ころに、滝口の指摘を受けた坂本が、一郎に対し、業務は所定の期限までに遂行すべきことを前提として、帰宅してきちんと睡眠を取り、それで業務が終わらないのであれば翌朝早く出勤して行うようになどと指導したのみで、一郎の業務の量等を適切に調整するための措置を採ることはなく、かえって、同年七月以降は、一郎の業務の負担は従前よりも増加することとなった。
その結果、一郎は、心身共に疲労困ぱいした状態になり、それが誘因となって、遅くとも同年八月上旬ころにはうつ病にり患し、同月二七日、うつ病によるうつ状態が深まって、衝動的、突発的に自殺するに至ったというのである。
原審は、右経過に加えて、うつ病の発症等に関する前記の知見を考慮し、一郎の業務の遂行とそのうつ病り患による自殺との間には相当因果関係があるとした上、一郎の上司である滝口及び坂本には、一郎が恒常的に著しく長時間にわたり業務に従事していること及びその健康状態が悪化していることを認識しながら、その負担を軽減させるための措置を採らなかったことにつき過失があるとして、一審被告の民法七一五条に基づく損害賠償責任を肯定したものであって、その判断は正当として是認することができる。
論旨は採用することができない。
(筆者注:以下は過失相殺に関して)
一 原審(東京高裁:筆者注)は、一審被告の賠償すべき額を決定するに当たり、民法七二二条二項の規定を適用又は類推適用して、弁護士費用以外の損害額のうち三割を減じた。
しかしながら、右判断のうち次の各点は、是認することができない。
二 一郎の性格を理由とする減額について
1 原審(東京高裁:筆者注)は、一郎には、前記のようなうつ病親和性ないし病前性格があったところ、このような性格は、一般社会では美徳とされるものではあるが、結果として、一郎の業務を増やし、その処理を遅らせ、その遂行に関する時間配分を不適切なものとし、一郎の責任ではない業務の結果についても自分の責任ではないかと思い悩む状況を生じさせるなどの面があったことを否定できないのであって、前記性格及びこれに基づく一郎の業務遂行の態様等が、うつ病り患による自殺という損害の発生及び拡大に寄与しているというべきであるから、一審被告の賠償すべき額を決定するに当たり、民法七二二条二項の規定を類推適用し、これらを一郎の心因的要因としてしんしゃくすべきであると判断した。
2 身体に対する加害行為を原因とする被害者の損害賠償請求において、裁判所は、加害者の賠償すべき額を決定するに当たり、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、民法七二二条二項の過失相殺の規定を類推適用して、損害の発生又は拡大に寄与した被害者の性格等の心因的要因を一定の限度でしんしゃくすることができる…
この趣旨は、労働者の業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求においても、基本的に同様に解すべきものである。
しかしながら、企業等に雇用される労働者の性格が多様のものであることはいうまでもないところ、ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等が業務の過重負担に起因して当該労働者に生じた損害の発生又は拡大に寄与したとしても、そのような事態は使用者として予想すべきものということができる。
しかも、使用者又はこれに代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う者は、各労働者がその従事すべき業務に適するか否かを判断して、その配置先、遂行すべき業務の内容等を定めるのであり、その際に、各労働者の性格をも考慮することができるのである。
したがって、労働者の性格が前記の範囲を外れるものでない場合には、裁判所は、業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求において使用者の賠償すべき額を決定するに当たり、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を、心因的要因としてしんしゃくすることはできないというべきである。
これを本件について見ると、一郎の性格は、一般の社会人の中にしばしば見られるものの一つであって、一郎の上司である滝口らは、一郎の従事する業務との関係で、その性格を積極的に評価していたというのである。
そうすると、一郎の性格は、同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものであったと認めることはできないから、一審被告の賠償すべき額を決定するに当たり、一郎の前記のような性格及びこれに基づく業務遂行の態様等をしんしゃくすることはできないというべきである。
この点に関する原審の前記判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。
三 一審原告(筆者注:両親)らの落ち度を理由とする減額について
1 原審(東京高裁:筆者注)は、一審原告らは、一郎の両親として一郎と同居し、一郎の勤務状況や生活状況をほぼ把握していたのであるから、一郎がうつ病にり患し自殺に至ることを予見することができ、また、一郎の右状況等を改善する措置を採り得たことは明らかであるのに、具体的措置を採らなかったとして、これを一審被告の賠償すべき額を決定するに当たりしんしゃくすべきであると判断した。
2 しかしながら、一郎の前記損害は、業務の負担が過重であったために生じたものであるところ、一郎は、大学を卒業して一審被告の従業員となり、独立の社会人として自らの意思と判断に基づき一審被告の業務に従事していたのである。
一審原告らが両親として一郎と同居していたとはいえ、一郎の勤務状況を改善する措置を採り得る立場にあったとは、容易にいうことはできない。
その他、前記の事実関係の下では、原審の右判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるというべきである。」
【判例のポイント】
1.使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう「注意する義務」を負う。
2.「使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者」は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである。
3.当該事例において、当該労働者の業務の遂行とそのうつ病り患による自殺との間には「相当因果関係」があり、その上司には当該労働者が恒常的に著しく長時間にわたり業務に従事していること及びその健康状態が悪化していることを認識しながら、その負担を軽減させるための措置を採らなかったことにつき「過失」があるとして、会社の「民法715条」に基づく損害賠償責任を肯定した。
4.身体に対する加害行為を原因とする被害者の損害賠償請求において、裁判所は、加害者の賠償すべき額を決定するに当たり、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、「民法722条2項の過失相殺」の規定を類推適用して、損害の発生又は拡大に寄与した「被害者の性格等の心因的要因」を一定の限度で斟酌することができる。
5.その趣旨は、「労働者の業務の負担が過重であること」を原因とする損害賠償請求においても、基本的に同様に解すべきものである。
6.ある業務に従事する特定の労働者の性格が、同種の業務に従事する労働者の「個性の多様さとして通常想定される範囲」を外れるものでない限り、「その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等」が業務の過重負担に起因して当該労働者に生じた損害の発生又は拡大に寄与したとしても、そのような事態は使用者として予想すべきものである。
7.労働者の性格が前記の範囲を外れるものでない場合には、裁判所は、業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求において使用者の賠償すべき額を決定するに当たり、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を、「心因的要因」として斟酌することはできない。
8.当該事例において、当該労働者の性格は、同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものであったと認めることはできないから、賠償すべき額を決定するに当たり、当該労働者の性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を斟酌することはできない。
9.当該事例において、損害は業務の負担が過重であったために生じたものであるところ、当該労働者は、大学を卒業して当該会社の従業員となり、独立の社会人として自らの意思と判断に基づき業務に従事していたのであるから、一審原告らが「両親として同居」していたとはいえ、その勤務状況を改善する措置を採り得る立場にあったとは、容易にいうことはできず、損害賠償額の決定つき斟酌すべきでない。
【ワンポイントレッスン】
やや長大で複雑な判決文なので、簡単に整理してみる。
まず、被害者の両親の主張は「息子の過酷な残業を知りながら適切な措置をとらなかった会社が悪い」である。
これに対する会社の反論は、「一応止めたんだけど、本人が残業を止めようとしなかった。こっちが悪いとしても、本人の生真面目な性格が影響してるし、御両親も知ってて止めさせなかったんだから、損害賠償額を低くするべき」である。
いわゆる「心因的素因」による過失相殺、「被害者側」の過失によるそれが問題となったわけだが、最高裁は当該事例へのあてはめで、いずれも退けた。
最高裁は、労働者の性格が、「個性の多様さとして通常想定される範囲」を外れるものでない限り、その「性格」及びこれに基づく業務遂行の態様等が、損害の発生又は拡大に「寄与」したとしても、そのような事態は使用者として予想すべきとして、過失相殺を否定している。
「個性の多様さとして通常想定される範囲」という、キーワードを覚えておこう。
本件は「心因的素因」に関するものだが、首が長いという「身体的素因」による過失相殺についても、最判平8.10.29(民法百選II92=判例六法・民法722条16番)という、重要判例が出ている。
民法722条2項類推適用について、両者をセットで押さえておこう。
余談だが、この最高裁判決のTVニュースで、御両親が涙ぐみながら「素晴らしい判決で感激しております」と述べていたのが、印象に残っている。
中央官庁のキャリアが、庁舎の窓から飛び降りたり、JR中央線に飛びこむのも珍しくなく、官民いずれにとっても労働条件改善は急務なのだが、なかなか進まない。
本判決のように裁判所が使用者に重い責任を負わせることは、一定の「抑止力」となるが、厚生労働省へ入る受験生のこれからの活躍を期待したい。
【試験対策上の注意点】
択一試験での出題可能性が高い。
判例六法・民法722条14〜17番は、まとめて押さえておこう。