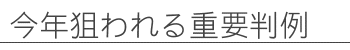【判旨】
「受贈者又は受遺者は、民法一〇四一条一項に基づき、減殺された贈与又は遺贈の目的たる各個の財産について、価額を弁償して、その返還義務を免れることができるものと解すべきである。
なぜならば、遺留分権利者のする返還請求は権利の対象たる各財産について観念されるのであるから、その返還義務を免れるための価額の弁償も返還請求に係る各個の財産についてなし得るものというべきであり、また、遺留分は遺留分算定の基礎となる財産の一定割合を示すものであり、遺留分権利者が特定の財産を取得することが保障されているものではなく(民法一〇二八条ないし一〇三五条参照)、受贈者又は受遺者は、当該財産の価額の弁償を現実に履行するか又はその履行の提供をしなければ、遺留分権利者からの返還請求を拒み得ないのであるから、右のように解したとしても、遺留分権利者の権利を害することにはならないからである。
このことは、遺留分減殺の目的がそれぞれ異なる者に贈与又は遺贈された複数の財産である場合には、各受贈者又は各受遺者は各別に各財産について価額の弁償をすることができることからも肯認できるところである。
そして、相続財産全部の包括遺贈の場合であっても、個々の財産についてみれば特定遺贈とその性質を異にするものではないから、右に説示したことが妥当するのである。」
【判例のポイント】
受贈者又は受遺者は、民法1041条1項に基づき、減殺された贈与又は遺贈の目的たる「各個の財産」について、「価額を弁償」して、その返還義務を免れることができる
【ワンポイントレッスン】
まず、本件の事例を簡単にアレンジして説明しよう(あくまでフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません)。
…上流階級の資産家であるXには、推定相続人として、A男、B女、C女、D男の4人の子供がいた。
死期が近いことを悟ったXは、「B女C女はブランド物を買い漁ってばかり。娘をちいと可愛がりすぎたかのお。かといって、末っ子のD男も甘えん坊で経営者の器ではないしなあ。よし、しっかり者のA男にワシの跡取りになってもらうか!」と、Xの全財産をAに包括遺贈(964条)した。
Xの死後、その財産である不動産・株式を全てAは引き継いだが、Bらは「イヤン、あの親父信じらんなーい」と自分らの遺留分について減殺請求してきた(1028条2号・1031条)。
これに対して、Aは、「不動産」は現物分割するが、偉大なる父が築いた会社の「株式」を出来の悪い妹達に渡すわけにはいかない、と「株式」についてのみ金銭による「価額弁償」をして、Aが株式を全部取得しようとした。
Aの主張は認められるか…
この点、最高裁は、一部の財産についてのみ、「価額弁償」を選択することを認めた。
なお、重判・解説によれば、「この事件の背後には(野ばら社の)経営権の争奪戦があり」とされており、会社の名前は爽やかだが、実の兄弟姉妹で骨肉の遺産争いが展開された模様である…。
【試験対策上の注意点】
「遺留分」関係は、相続では重要事項である。
択一対策として、条文知識とあわせて、判例の立場を押さえておこう。