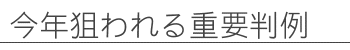【論点】
小作地に対する宅地並み課税と小作料増額請求
【判旨】
「1 本件は、都市計画法7条1項に規定する市街化区域内にある農地を所有し、上告人らに賃貸している被上告人が、その農地に対する固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の合計額が平成4年度以降大幅に増加したことを理由として、農地法(以下「法」という。)23条1項に基づき、上告人らに対して小作料を増額する旨の意思表示をし、同5年分及び同6年分の小作料の額がその意思表示に係る額であることの確認を求める事件である。
市街化区域内にある農地の固定資産税等については、昭和46年に行われた地方税法の改正によって、その課税標準となるべき価格を当該農地と状況が類似する宅地の課税標準とされる価格に比準する価格によって定めた上で、農地に対して課する固定資産税等の特例を適用せず、上記課税標準となるべき価格に基づき算出した金額を課税標準として課税を行う措置(以下この措置を「宅地並み課税」という。)が定められた。この措置は同48年度に実施されて以降、その対象が段階的に拡大されてきたところ、本件の農地に対する固定資産税等の額が大幅に増加したのは、平成3年に行われた地方税法の改正により、同4年度以降、市街化区域内の農地から生産緑地地区の区域内の農地等を除いたもの(以下「市街化区域農地」という。)のうち、いわゆる3大都市圏の特定市に所在するすべての市街化区域農地について、宅地並み課税がされるようになったことによるものである(同3年法律第7号による地方税法附則19条の2、19条の3、29条の5、29条の6等の改正)。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
(1) 被上告人は、第1審判決別紙物件目録記載(一)の土地(以下「本件土地(一)」という。)及び同目録記載(二)の土地(以下「本件土地(二)」という。本件土地(一)と合わせて、以下「本件各土地」という。)を所有し、上告人Aは本件土地(一)を、同Bは本件土地(二)を、それぞれその先々代の時代から賃借して耕作している。上告人Aは、本件土地(一)で稲作等を行っており、肥料代、苗代、農薬代等の経費を除いて本件土地(一)から得られる利益は年額3万円程度である。上告人Bは、本件土地(二)で自家消費用の野菜等を栽培している。
(2) 本件土地(一)の小作料の額は、昭和56年から同63年までは年額2万1794円、平成元年以降は年額2万0312円であり、本件土地(二)の小作料の額は、昭和56年から同63年までは年額1万6522円、平成元年以降は年額1万5400円であった。上記各小作料は、おおむね法24条の2第1項に基づいて天理市農業委員会が定めた小作料の標準額に沿って算出されたものであった。
(3) 本件各土地は、いずれも市街化区域内の農地であったが、その固定資産税等については、従前は、宅地並み課税がされていなかったところ、平成3年の地方税法の改正により、生産緑地法に定める生産緑地地区に指定された場合を除き、同4年度以降、宅地並み課税の対象とされることになった。
(4) 上記地方税法の改正に当たり、生産緑地地区の指定は平成4年12月末日までに行うこととされ、各市町村では、農地所有者等の意向を把握して、必要な都市計画の手続を行うことになった。被上告人も、本件各土地につき、生産緑地地区の指定を受けることを希望し、上告人らに対して生産緑地地区の指定に必要とされる賃借人としての同意を求めた。しかし、上告人らがこれに同意しなかったために、生産緑地地区の指定を受けることができなかった。
(5) その結果、本件土地(一)に対する固定資産税等の額は、平成4年度及び同5年度は11万9119円、同6年度は12万5074円に、本件土地(二)に対する固定資産税等の額は、同4年度及び同5年度は10万0240円、同6年度は12万5241円にそれぞれ増加した。なお、宅地並み課税がされなかったとした場合の同4年度の固定資産税等の額は、本件土地(一)は2万0100円、本件土地(二)は1万6661円であった。
(6) 上告人らが生産緑地地区の指定に同意しなかったのは、生産緑地地区の指定によって土地の評価額が低く抑えられ、将来の合意解約の際の離作補償の点で不利になることを危ぐしたからであった。
(7) 上記宅地並み課税の結果、固定資産税等の額が小作料の額を上回るいわゆる「逆ざや現象」が起こったことから、被上告人は、固定資産税等の額が増加したことを理由として、上告人らに対し、平成4年12月、同5年分の本件土地(一)の小作料の額を年額11万9119円に、同年分の本件土地(二)の小作料の額を年額10万0240円に増額する旨の意思表示をし、さらに、同5年12月、同6年分の本件各土地の小作料の額をそれぞれ年額15万円に増額する旨の意思表示をした。
3 原審(筆者注:大阪高裁)は、上記事実関係の下において、次のとおり判示し、被上告人の請求を宅地並み課税によって増加した固定資産税等の額の限度で認容すべきものとした。
(1) 法23条1項等の規定は、小作料の額は主として当該小作地の通常の収益を基準として定めるべきものとしているが、小作地に対して宅地並み課税がされた場合には、事案によっては、固定資産税等の額が増加したことが、同項にいう「その他の経済事情の変動」に該当するものと解すべきである。なぜならば、固定資産税等の額と小作料の額との間に生じた逆ざや現象を解消することが一切許されないとすると、賃貸借という有償契約でありながら、賃借人が小作料名下に支払う金員が農地の使用の対価といえなくなる不当な結果が生じるからである。
(2) 本件においては、上告人らは、生産緑地地区の指定を受けたとしても本件各土地を従前どおり耕作できる点で何ら不利益を被るものではないにもかかわらず、将来の離作補償の点で不利になるとの利己的な思惑から、被上告人が希望しているのに生産緑地地区の指定に同意しなかったとの事情があり、この事情の下では、信義、公平の原則により、本件各土地の小作料は、被上告人の増額の意思表示により、増額を求める年度の固定資産税等の額と同額に増額されたものと認めるのが相当である。
(筆者注:以下が最高裁の見解)
4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
(1)ア 法は、昭和45年に行われた改正(同45年法律第56号による改正。同年10月1日施行)によって、同14年の小作料統制令による統制以来行われてきた小作料の最高額の統制を廃止し、小作料を当事者の自由な決定にゆだねるとともに(ただし、同55年9月30日まで統制を存続する旨の経過規定がある。同45年法律第56号附則8項、同45年政令第255号附則6項)、当初定められた小作料の額がその後の事情の変更によって不相当となった場合における小作料の増減請求に関する規定として23条を置き、同条1項は、「小作料の額が農産物の価格若しくは生産費の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により又は近傍類似の農地の小作料の額に比較して不相当となつたとき」には、当事者は、将来に向かって小作料の額の増減を請求することができる旨を規定した。この規定は、継続的契約関係における当事者間の利害を調整しようとする規定であって、借地借家法附則2条により廃止された借地法12条1項や借地借家法11条1項と同一の趣旨のものであるが、これらの規定が土地に対する租税その他の公課の増減を地代の額の増減事由として明定しているのに対し、経済事情の変動の例として「農産物の価格若しくは生産費の上昇若しくは低下」を挙げているにすぎず、小作地に対する公租公課の増減を増減事由として定めていない。また、法は、小作料の統制廃止後においても、不当に高額の小作料が取り決められて耕作者の地位の安定を害することがないようにするため、上記改正に当たり新たに小作料の標準額の制度を設け、農業委員会は、小作料の額の標準となるべき額(小作料の標準額)を定め(24条の2第1項)、契約で定める小作料の額が小作料の標準額に比較して著しく高額であると認めるときは、当事者に対し、その小作料を減額すべき旨を勧告することができるものとした(24条の3)。そして、小作料の標準額を定めるに当たっては、「通常の農業経営が行なわれたとした場合における生産量、生産物の価格、生産費等を参酌し、耕作者の経営の安定を図ることを旨としなければならない」と規定した(24条の2第2項)。さらに、法は、災害等による一時的な減収があった場合の耕作者の地位の安定を図るために、小作料の額が不可抗力により、田にあっては収穫された米の価額の2割5分、畑にあっては収穫された主作物の価額の1割5分を超えることになった場合には、小作農は、上記割合に相当する額になるまで小作料の減額を請求することができる旨を定めている(24条)。
これらの規定に加え、法が耕作者の地位の安定をその目的の一つとしていること(1条)を合わせて考慮すると、法は、小作料の統制廃止後においても、耕作者の地位ないし農業経営の安定を図るため、当該農地において通常の農業経営が行われた場合の収益を基準として小作料の額を定めるべきものとしていると解するのが相当であり、法23条1項もこの趣旨に沿って解釈すべきである。そして、前記のように昭和46年に農地に対する宅地並み課税の制度が創設され、同48年度以降、その対象が拡大されてきた過程においても、法の上記各規定には何らの変更も加えられなかったのであるから、宅地並み課税の対象とされる農地の小作料の額についても、上記説示と異なるところはないというべきである。
イ また、農地に対する宅地並み課税は、市街化区域農地の価格が周辺の宅地並みに騰貴して、その値上がり益が当該農地の資産価値の中に化体していることに着目して導入されたものであるから(最高裁昭和52年(オ)第773号同55年1月22日第三小法廷判決・裁判集民事129号53頁参照)、宅地並み課税の税負担は、値上がり益を享受している農地所有者が資産維持の経費として担うべきものと解される。賃貸借契約が有償契約であることからみても、小作料は農地の使用収益の対価であって、小作農は、農地を農地としてのみ使用し得るにすぎず、宅地として使用することができないのであるから、宅地並みの資産を維持するための経費を小作料に転嫁し得る理由はないというべきである。
ウ もっとも、農地所有者が宅地並み課税による税負担を小作料に転嫁することができないとすると、農地所有者は小作料を上回る税を負担しつつ当該農地を小作農に利用させなければならないという不利益を受けることになる。しかし、宅地並み課税の制度目的には宅地の供給を促進することが含まれているのであるから、農地所有者が宅地並み課税によって受ける上記の不利益は、当該農地の賃貸借契約を解約し、これを宅地に転用した上、宅地として利用して相応の収益を挙げることによって解消することが予定されているのである。また、賃貸借契約の解約後に当該農地を含む区域について生産緑地地区の指定があったときは、宅地並み課税を免れることができるから、農地所有者は、これによっても不利益を解消することができる。そして、当該農地の賃貸借契約について合意解約ができない場合には、農地所有者は、具体的な転用計画があるときには法20条2項2号に該当するものとして、あるいは当該農地が優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である市街化区域内にあることや逆ざや現象が生じていることをもって同項5号に該当するものとして、解約について知事の許可(同条1項)を申請し、具体的事案に応じた適正な離作料の支払を条件とした知事の許可を得て(同条4項。農地法施行規則14条1項7号参照)、解約を申し入れることができるものと解される(民法617条)。
農地所有者には宅地並み課税による不利益を解消する方法として、上記のとおりの方途が存在するのに対し、宅地並み課税の税負担を小作料に転嫁した場合には、小作農にはその負担を解消する方法が存在せず、当該農地からの農業収益によって小作料を賄うこともできないことから、小作農が離農を余儀なくされたり小作料不払により契約を解除されたりするという事態をも生じ兼ねないのであって、小作農に対して著しい不利益を与える結果を招くおそれがあるというべきである。
(2) 以上説示したところからすれば、小作地に対して宅地並み課税がされたことによって固定資産税等の額が増加したことは、法23条1項に規定する「経済事情の変動」には該当せず、それを理由として小作料の増額を請求することはできないものと解するのが相当である。これに反し、農地所有者が宅地並み課税による固定資産税等の額の増加を理由として小作料の増額を請求した事案において、小作料の増額を認めた原審の判断を正当なものとして是認した最高裁昭和58年(オ)第1303号同59年3月8日第一小法廷判決は、変更すべきものである。
(3) 生産緑地法3条1項の規定による生産緑地地区の区域内の農地は宅地並み課税の対象から除外されるが(地方税法附則19条の2第1項)、当該農地に対抗要件を備えた賃借人がいる場合には生産緑地地区に関する都市計画の案について賃借人の同意が必要とされているため(生産緑地法3条2項)、当該農地の所有者が生産緑地地区の指定を受けることを希望したとしても、賃借人が同意しない限り、当該農地を含む区域が生産緑地地区に指定されることはない。しかし、所有者が生産緑地地区の指定を受けることを希望している場合に、賃借人にこれに同意すべき義務を認める規定は見当たらない。また、生産緑地地区の区域内の農地が賃貸されているときにこれを農地として管理する義務を負うのは、当該農地について使用収益権を有する賃借人であり(同法7条1項)、生産緑地における農業経営は原則として30年間継続することが予定されているのであるから(同法10条参照)、同意をするかどうかは各自の生活設計にわたる事柄というべきであって、賃借人の意向が尊重されるべきものである。そうすると、賃借人には同意をすべき信義則上の義務があるということはできず、上告人らが同意をしなかったことをもって、信義、公平に反するとして、これを理由に小作料の増額を認めることもできないというべきである。
(4) そして、被上告人は、小作料の増額を請求する理由として、本件各土地に対して宅地並み課税がされた結果固定資産税等の額が増加したことのみを主張し、他に小作料を増額すべき事由を主張しないから、被上告人の請求はいずれも理由がない。
5 以上によれば、原審の前記判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、その違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり、原判決のうち上告人らの敗訴部分は破棄を免れない。そして、前記説示によれば、被上告人の請求をいずれも棄却した第1審判決は正当であるから、前記敗訴部分につき被上告人の控訴を棄却することとする。」
【判例のポイント】
1.小作地に対して宅地並み課税がされたことによって固定資産税等の額が増加したことは、農地法23条1項(現在の21条1項)に規定する「経済事情の変動」には該当せず、それを理由として小作料の増額を請求することはできない。
2.農地所有者が宅地並み課税による固定資産税等の額の増加を理由として小作料の増額を請求した事案において、小作料の増額を認めた原審の判断を正当なものとして是認した判例を変更。
【ワンポイントレッスン】
以下の2つの条文を比較して欲しい。
借地借家法11条1項本文
「地代又は土地の借賃…が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる」
農地法21条1項本文(事件当時の23条に対応)
「小作料の額が農産物の価格若しくは生産費の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により又は近傍類似の農地の小作料の額に比較して不相当となつたときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かつて小作料の額の増減を請求することができる」
借地借家法では「土地に対する租税その他の公課の増減」が明文で挙げられているのに対して、農地法では意図的に外されている。
この点につき、田山教授は「農地課税においては、農業収益を前提とした評価に基づく税以外は考えられず、その変動要素は既に課税標準額の構成要素に折込済である。従って、バイオテクノロジーの飛躍的発展等により農地価格が急上昇するようなことがない限り、予想外の増税はあり得ない」と説明する(重判・解説)。
最高裁は、「農地所有者が宅地並み課税によって受ける上記の不利益は、当該農地の賃貸借契約を解約し、これを宅地に転用した上、宅地として利用して相応の収益を挙げることによって解消することが予定されている」ことなどを挙げ、結論として、小作地に対して宅地並み課税がされたことによって固定資産税等の額が増加したことは、農地法23条1項(現在の21条1項)に規定する「経済事情の変動」には該当せず、それを理由として小作料の増額を請求することはできない、とした。
【試験対策上の注意点】
特別法の判例なので、ざっと見ておけば足りる。